【若い世代視点からのライフデザインに関する検討会(第2回)】で意見交換された【ウェルビーイングを実現するライフデザイン】
こども家庭庁には、2025年7月から長官官房総務課に【ライフデザイン室】が設置されました。
そして、ライフデザイン室が事務局をつとめる【若い世代視点からのライフデザインに関する検討会】は、2024年度加藤鮎子大臣・三原じゅん子大臣主宰として設置された【若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ】の8回の会議を踏まえた【議論のまとめ(最終報告)】を受けて、①若い世代が将来設計をする上で直面している社会的障壁、②望んでいるライフデザイン支援の在り方、③それらを踏まえた環境・社会づくりなどについて、若い世代の視点から議論を深め、検討するため設置されているものです。
私は、こども家庭庁参与として、8月29日に開催された第2回の会議に陪席しました。
本検討会はの構成員は、座長の柴田悠・京都大学大学院教授はじめ有識者5名と大学生・大学院生。会社員7名で、会議室とオンラインのハイブリッドで開催されています。
会議前に、小室淑恵・(株)ワーク・ライフ・バランス代表取締役社長が初めて会議室で参加されました。
小室さんとは、内閣府に初めて設置された【こども・子育て会議】で委員をご一緒したり、現在は休止している【にっぽん子ども子育て応援団】の企画委員をご一緒してきたご縁があります。
柴田座長も小室さんとは日常的にはネットで情報交換しているところ、今日は久しぶりにリアルでおめにかかったということで、宮木由貴子・(株)第一生命経済研究所常務・ライフデザイン研究部長・首席研究員を交えて懇談しました。
この日は、まずは、【ライフデザインの取組の背景と意義に関する前回の振り返り】をしました。
前回の意見の中には、次のような意見がありました。
・現代社会は情報が溢れていて不安を煽られる傾向があり、ネットを経由して様々な視点・情報に触れることができ、それが自分に当てはまるのかも分からず、これが正しいのかも精査が必要になっているので、正しい情報を知る機会が欲しい。
・キャリア以外の本当のライフ・人生の部分をどうやって学んでいけばいいのかが分からない。
・自分の中のものを引き出して、整理したりとか、それを自分の中だけでなく、他者と一緒に答え合わせをする中で、深めていくみたいなところで、ライフデザインって意義があると思う。
・ライフデザインを通して、他者の人生に寄り添うことや理解し合うこと、自分が良いと思っている自分の経験に基づいた生き方は、必ずしも他者に必ず当てはまるものではない、ということを学ぶ機会にもなるのではないかと思う。
・ライフデザインをすることで立てた計画はうまくいくものばかりではない。「計画通りいかないと良くない」とならないように受け止められるようにしないといけない。
この日も、思いがけず親を亡くしたこども、配偶者を亡くした若者など、予期せぬことも起こる人生にあって、ライフデザイン通りにいかないときに、どのように対応すべきかについての問題提起がありました。
私は、若い頃、大学院を修了してなるべく順調に就職したいと描いていましたが、実際に就職できたのは31歳、結婚についてもできれば20代半ばでと想定していましたが、それも31歳、こどもを出産しても仕事は継続したいと計画してそれを実現できてはいましたが、上のこどもが10歳、下のこどもが6歳の時にシングルマザーとなりました。
さらには大学教員として職業生活を全うしたいと思っていましたが、突然の周囲の要請と悩んだ後の自身の決断で、40代までの自身の【ライフデザイン】の中には片鱗さえもなかった【まさかの三鷹市長】に挑戦し、おかげさまで4期16年務めることになりました。
昭和から平成の時代に、私なりに【ライフデザイン】を構築していましたが、予期せぬことが続き、常に対応を余儀なくされてきました。
しかしながら、【ライフデザイン】を意識していたからこその異業種であれ職業の継続と、結婚・出産・子育て・子育てを支えてくれた両親の見送りをすることができたのではないかと振り返っています。
2回目の会議でも、若者構成員がご本人や友人等の、大学のキャリアセンターの取組みの相違なども含めて、若者の生の意見を披歴しました。
有識者構成員からの意見を含めて、【ライフデザインは単線系ではないこと】、【事前の想定以外のできことがあったときに、それを踏まえて適切に対応していくことの必要性】も確認できるようにすること、高校・大学よりも前の早期のライフデザインに関する学びの機会が有用であることなどが提起されました。
次に、【若い世代のライフデザイン支援の求める姿と課題】について、①ライフデザインのタイミング、②情報チャンネル・ロールモデルとの接点、③
必要な情報・支援について意見交換が行われました。
第1回で発言された意見を踏まえつつ、【ライフデザインは、常に見直していくものであるが、ライフデザインを特に考えるきっかけとなる時期があり、そのタイミングで必要な支援が充実しているとよい】【特にライフステージが大きく変化する直前の「大学生等(就活前~中) 」、「中堅社会人・前期」がニーズもあり、解像度高くライフデザインを考える上で効果的なタイミング】について意見交換が行われました。
特に、ライフデザインのタイミングについては、若者委員から、自身の経験と重ね合わせたときのタイミングについて、実情が紹介されました。
また、天野馨南子・(株)ニッセイ基礎研究所人口動態シニアリサーチャーからは、地方創生の観点から、自治体は地元に若者に残ってほしいとの考え方で働きかけるが、若者がライフデザインを学ぶことを通して、かえって地元を離れて大都市部に転出可能性が高まるというジレンマ・課題についても丁寧に検討する必要性を提起されました。
この日は、宮木由貴子首席研究員から【ウェルビーイングを実現するライフデザイン】についての報告がありました。
第一生命経済研究所のこれまで30年にわたる【ライフデザイン白書】の発行等の調査研究を踏まえて、ライフデザインやその支援のこれまでの変遷や若い世代やそれに関わる関係者の意識・ニーズの変化等について説明がありました。
特に、【なぜライフデザインが必要なのか?】については、従来の【なんとなく“to be”が社会で共有されていた時代】においては、【やり方の追求(to do先行型):どううまくやるか(well-doing)】が先行していたところ、【“to be”が社会で共有されておらず、自分で考える時代】においては、【あり方を追求(to be先行型):どうありたいか(well-being)】が重要となり、ここに、まさに【ライフデザインの重要性】があることを説明されました。
第3に、【ライフデザイン支援に関する若い世代また世代間の意識等を定量的に把握】するために実施を予定している【アンケート調査設計】に関しても意見交換が行われました。
千葉大学の大学院生の郡司日奈乃構成員や島津明人・慶應義塾大学総合政策部教授をはじめ皆様から有意義なアンケート調査の実施に向けて、質問紙の文章表現や、ライフデザイン等の用語の定義を示すことなど、調査対象者が回答しやすい方向と調査結果の有意義な分析のための提案が発言されました。
最後に、会議の後半の構成員のご意見を傾聴されていた三原じゅん子大臣から、【若い委員からは、今のご自身の状況と重ね合わせた、まさに当事者のニーズや、日頃感じていること等率直に意見をいただいたこと】、【有識者構成員からは、求める姿を実現する上での課題認識と解決に向けて、具体的な視点を提示いただいたこと】、宮木構成員から【ライフデザインやその支援の変遷、それに関連する若者を取り巻く環境変化等のご説明をいただいたこと】に感謝が表明されるとともに、ご意見をいただいた【アンケート調査】によって【若い世代の人生の選択をめぐる認識や社会に求めていることを定量的に明らかにし、社会の理解を広めていく】ために生かしていきたいと発言されました。
2時間余りの【若い世代視点からのライフデザインに関する検討会】に陪席して、こども・若者はもちろんんこと、各世代の【ウェルビーイングを実現するライフデザイン】の実現の必要性を確認しました。


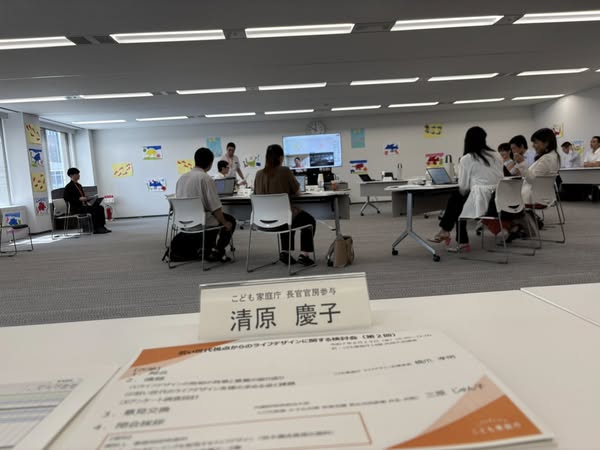
 清原慶子 Official Website
清原慶子 Official Website




