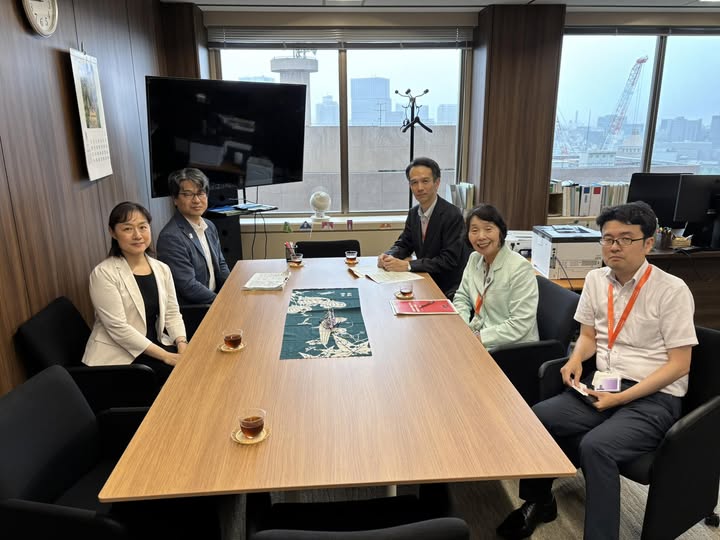【こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会】の構成員として出会った【愛媛県】と【愛知県】の【愛】のある県の子育て支援課長
私は、市長経験者として、2024年度にこども家庭庁に設置された【こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会】の構成員を務めました。
【こども誰でも通園制度】については、2025年度に【子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業】として制度化し、実施自治体の増加を図った上で、2026年度から【子ども・子育て支援法に基づく新たな給付】として全国の自治体において「保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等に通っていない0歳6か月~満3歳未満」のこどもを対象に実施することとされています。
そこで、2024年度は、2023年度からの試行自治体の実態を踏まえつつ、2025年度及び2026年度以降の制度の在り方について検討しました。
そして、昨年の12月26日に開催された第4回会議では、【とりまとめ案】が審議されました。
その際、私は、1点目として、「検証に基づく改善が今後も必要」であることを指摘し、2点目として、0歳6か月未満のこどもについては、「伴走型相談支援等を基本として、産後ケア事業、家庭支援事業、そして、一時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業及び親子関係形成支援事業等、様々な支援策を、必要に応じ、こども家庭センターで作成するサポートプラン等により適切に組み合わせながら支援していくことが重要であると発言しました。
3点目には、「県の支援が必要であり、有効である」ということへの期待を申しました。もちろん、【こども誰でも通園制度】は、基礎自治体、市区町村が主体の事業と位置づけられていますが、それが円滑に進むためには、都道府県の支援、そして、確実な制度づくりによる連携が求められていると思います。円滑で質の高い保育を実践するには、保育士、幼稚園教諭等、職員の資質の向上が必要で、あるいは施設整備についても、国の支援だけではなくて、総合的な子ども・子育て支援の都道府県の取組が重要です。この間、都道府県が格別に、いい意味で「コンペティションの競争」ではなくて、「コ・クリエーションの共創」で、国と連携しながら、こどもたちのた
めの研修や施設整備に取り組んでいると発言しました。
加えて、事務局に伺ったところ、2024年度に【愛知県】では県が主導で市町の方を集めて、【誰でも通園制度について意見交換、情報交換】したということを紹介しました。
そして、2025年度に入り、7月18日に、【こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会】が設置され、21名の構成員の1人として私は引き続き参加しました。
21名の構成員には、秋田喜代美座長をはじめ有識者や事業者の皆様に加えて、秋谷允・松戸市こども部保育課長、小野敏伸・福岡市こども未来局事業調整課長、首長正博・栃木市こども未来部長、原田樹・七尾市健康福祉部子育て支援課長、万井勝徳・高槻市こども未来部子育て企画官という5市の職員の皆様が参加しています。
今回は、市区に加えて、県職員である阿部淳子・愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課長と森川明子・愛知県福祉局子育て支援課長が参加されました。
私が県の基礎自治体への支援と共創の取組が必要と発言したことが、構成員の構成に反映されて幸いに思います。
第1回の会議では、「こども誰でも通園制度」を「こどもまんなか」の視点で推進していくためには、「こども誰でも通園制度」の最前線の基礎自治体を支える広域自治体である「都道府県の役割」が極めて重要でございます。「都道府県の役割」として、「実施に向けた予算確保、市区町村への本格実施に向けた助言・支援(広域的な対応を含む)、市区町村の実施状況等に関する情報集約」と項目が例示されています。先ほど愛知県の委員さんも言っていただいた、特に「広域的な対応」を含む、あるいは「地域格差なく進めていく」ときには、「広域自治体の都道府県の役割」が極めて重要です。
議員立法による「こども基本法」第3条には、こども政策の6つの理念が明記されていて、2番目の項目は次のように書かれています。「全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること」、次なのです。「愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること」とあり、法律に「愛」という文字が明確に議員立法で書かれているわけですが、本日「愛媛県」と「愛知県」ろいうともに県名に「愛のある県」から出席されています。これは偶然と思いますし、2県とも本当に先駆的に進められているわけですが、私たちも本当に愛を込めて検討していきたい」と発言しました。
そのあと、愛媛県の阿部課長は、「愛ある愛媛県といたしましては、こどもまんなか
の政策におきまして、この制度を円滑に導入したいと考えております。」と呼応してくださいました。
この日、愛媛県の阿部課長とは会議室でお目にかかることができました。
愛知県の森川明子課長にお会いしたいと思っていましたところ、8月初旬に、愛知県福祉局こども家庭推進官の櫻井敬三さんとご一緒にこども家庭庁を訪問され、水田功・長官官房審議官(総合政策等担当)とこども政策について対話される機会に、私も江口友之・地方連携推進室長と一緒に同席させていただき、お目にかかることができました。
お2人は「県の名前に愛のある愛知県」として、大村知事を中心に【こども政策】の充実に取組むとともに、特に若者の【ライフデザイン】についても注目して取り組んでいるとのことです。
私は、スタジオジブリと連携して【三鷹市立アニメーション美術館・三鷹の森ジブリ美術館】の運営の経験から、愛知県には【ジブリパーク】があるので、その活用について伺いました。
すると、すでに、ジブリパークで結婚支援のイベントを開催したところ、応募者が多数で抽選になったとの事例を伺いました。
今後、森川課長とは【こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会】でご一緒に、自治体と事業者の現場に根差した【こどもまんなか】の取組みとすべく審議に参加することになります。
その心合わせもさせていただいた出会いでした。
 清原慶子 Official Website
清原慶子 Official Website