【いじめ重大化要因等の分析・検討会】座長としてとりまとめた、いじめ重大化予防のための【留意事項集】と【研修用事例集】
- 2025/11/21
- 日記・コラム, 審議会・委員会等
- いじめ, いじめ重大事態, こども家庭庁, 文部科学省, コミュニティスクール, 学校運営協議会, 教員, スクールカウンセラー, スクールソーシャルワーカー
私は、2025年1月に発足した【いじめ重大事態分析・検討会】の座長をつとめ、9月までの9回の会議を重ねました。
本検討会は、2024年11月開催の【いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議】で、昨年公表された【令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果】を踏まえて、主として量を把握する調査に加えて、【いじめ重大事態調査に基づく質的調査】を使命として設置されました。
本検討会は、こども家庭庁支援課総務課を主たる事務局として、文部科学省初等中等教育局児童生徒課と連携して運営されました。
検討会の構成員は以下の皆様です。(敬称略)
・新井肇:関西外国語大学外国語学部教授
・石川悦子:こども教育宝仙大学教授
・栗山博史:弁護士(神奈川県弁護士会所属)
・澤田真由美:株式会社先生の幸せ研究所代表取締役
・野澤和弘:植草学園大学副学長(教授)、(一社)スローコミュニケーション代表
・村宮汐莉:地域・教育コーディネーター
・清原慶子:杏林大学客員教授、前東京都三鷹市長
そして、11月21日に、こども家庭庁で【いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議(第5回)】が開催され、本検討会議がとりまとめた【いじめの重大化を防ぐための留意事項集】及び【いじめの重大化を防ぐための研修用事例集】が報告され、公表されました。
議長はこども家庭庁支援局の齊藤馨局長と文部科学省初等中等教育局の望月禎局長です。
これに先立って、こども家庭庁及び文部科学省関係の記者の皆様に、本検討会と留意事項集及び研修用事例集について説明する機会に、私は参加しました。
出席したのは、こども家庭庁支援局の小野総務課長と星企画官、文部科学省初等中等教育局児童生徒課の千々岩課長、(公社)こどもの発達科学研究所の和久田学所長と私です
その際、私は、検討会の座長として、以下の5点について報告しました。
1.検討会の取組みの特徴は以下の通りです。
①検討会の分析・検討の目的は、分析の結果得られたいじめの端緒・予兆や重大化要因等を各学校の設置者及び学校における未然防止等に活用することであすり、構成員は、【いじめの予防、早期発見と適切な対応により、重大化を防ぎたい、何よりもこどもたちの尊い命を守り、心身ともに傷つくようなことを無くしたい、減らしたいとの強い思いで取組みました。
②分析の対象は国に提供された約400件の重大事態調査報告書の中から32件について分析しました。
実は、私は令和5年度から文部科学省初等中等教育局長とこども家庭庁支援局長の連名による委嘱を受けて【いじめ防止対策協議会】委員をつとめており、2023年度には、国に寄せられたいじめ重大事態調査報告書を文部科学省及びこども家庭庁の事務局職員が分析して、会議ではその報告を受け、2024年8月には【いじめの重大事態の調査に関するガイドライン改訂版】を策定しました。
2.検討会の構成員による目標の共有と多角的視点での分析によるきめ細かい留意点を提示しました。
●構成員は就任当時大学4年生の若者、いじめ重大事態調査委員会の委員の経験者、障害児に詳しい専門家など、多様な7名で構成されました。
●構成員は、何よりも【いじめの重大事態】を予防したい、こどもたちの尊い命と心を守りたい、【こどもまんなか】の視点から、学校をよりよい環境にしたいとの思いを共有しつつ、(公社)子どもの発達科学研究所の協力を得ながら、謙虚に重大事態調査の分析を行い、こどもたちの思いに寄り添うことに努めつつ、いじめの予防に向けて意見交換をしました。
●毎回、2時間が足りないほどの文字通り活発な意見交換が行われました。各回の会議で、構成員同士が触発されつつ、それぞれの構成員が何度も発言して、真に多角的に内容を吟味し、以下の15項目の留意点を抽出しました。
1 いじめの重大化を防ぐための対応
【1-1】 児童生徒の言葉の聴き取りと深い理解に基づく対応
【1-2】 言葉以外のサインの察知
【1-3】 特別な支援を必要とする児童生徒に対する理解
【1-4】 特別な支援を必要とする児童生徒に対する支援
【1-5】 児童生徒が傍観者にならないための環境づくり
【1-6】 いじめ対策における組織的対応
【1-7】 いじめを行った児童生徒への対応
【1-8】 地域の関係機関との連携
【1-9】 保護者・地域と協働したいじめ対策
【1-10】 法、基本方針、ガイドラインに基づく対応
2 いじめの重大化につながり得る要素•特徴
【2-1】 教職員の学級環境、児童生徒間トラブルへの慣れ
【2-2】 進級・進学、転校等の環境の変化
【2-3】 交際関係の開始・解消、性的ないじめ
【2-4】 インターネット・SNSにおけるいじめ
【2-5】 閉鎖的な集団におけるいじめ
●各留意事項にまとめられている【対応のポイント】には、各構成員の指摘や提案が吟味され、最大限反映され、列挙されています。
3.こどもたちへ、教職員・教育委員会等の皆様へ、首長部局の皆様へ、保護者の皆様へ、地域の皆様へのメッセージを作成しました。
●構成員の皆様との検討の過程で、この留意事項は、第一義的には教職員・教育委員会の皆様と共有して、学校や学級で日常的に役立てていただきたいと思いました。
●それと同時に、いじめを受けるこども、いじめをするこども、傍観するこどもたちにも、しっかりとメッセージを発信したいとの思いを強くしました。
さらに、社会全体でいじめの予防、重大化阻止をはかるために、首長部局の皆様へ、保護者の皆様へ、地域の皆様へのメッセージを発信することにしました。
●たとえば、こどもたちには、【相手の人格と命を尊重し、何かあったら“伝える”ことがいじめを止める第一歩に】とメッセージをまとめました。
けれども、「相談できないこどもたち」もたくさんいるとの構成員の気づきから、次のようにしました。
4.留意点の他に【Ⅱいじめの防止・重大化予防のための全ての児童生徒にとって安全で安心な学校・学級づくり】を含めました。
私たちは、15項目の留意点とは別に、日常的に【こどもまんなか】の視点で【児童生徒にとって安全で安心な学校・学級づくり】がなされていなければ、こどもたちが気軽に相談することはできないし、いじめなどのこどもたちの悩みや困難に寄り添うことは難しいと考えて、以下の項目を提示しました。
① 多様性に配慮した学校・学級づくり
② 対等で自由な人間関係を構築する居場所としての学校・学級づくり
③ 自分が誰かの役に立っていると思える自己有用感を育む
④ 「困った、助けてほしい」と言える環境づくり
5.いじめの重大化を防ぐための研修用事例集の活用を期待します。
本事例集では、まずは、教職員の皆様に、掲載している架空の事例を素材に、さらに、実際に身近で起きたいじめの重大事態の事案や学校の設置者が公表している重大事態調査報告書を題材として、更なる事例検討を行い、同様の事態の発生防止につなげることも有効と考えられます。
また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、コミュニティ・スクール支える学校運営協議会の委員の皆様、私も地域のスクールサポーターをしていますが、そうしたボランティアの皆様を含めて、いじめ事案について組織的対応を行う上で関係する幅広い皆様の参加を促していただくことを期待します。
いじめ対策は、学校だけで対応する問題ではなく、保護者やこどもをめぐる関係機関、地域住民なども含めた関係者が連携し、社会総がかりで取り組むことが重要と考えるからです。
私は、まずはいじめの問題に直面しているこどもを守りたいと思います。
同時に、教職員が決して孤立しないように、チーム学校、チーム地域社会での取組みが必要と考えます。
そして、保護者をはじめ、地域の方がいじめの防止や重大化予防について【自分事】【わがこと】として、学び合う機会にも活用していただくことをお願いします。
皆様、ぜひ、留意事項集・研修用事例集をお読みください。
●いじめの重大化を防ぐための留意事項集
https://www.cfa.go.jp/.../20251114_councils_ijime...
●いじめの重大化を防ぐための研修用事例集
https://www.cfa.go.jp/.../20251114_councils_ijime...
*写真はこども家庭庁支援局の齊藤馨局長と


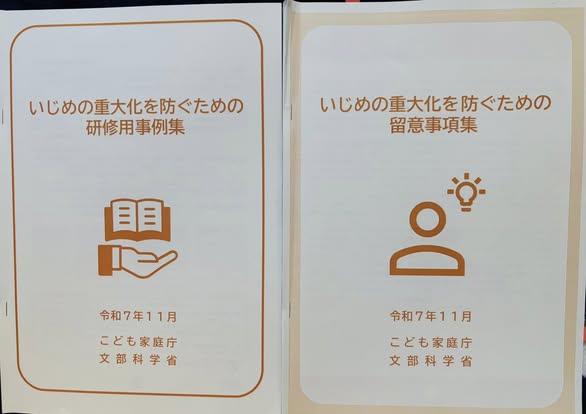
 清原慶子 Official Website
清原慶子 Official Website




