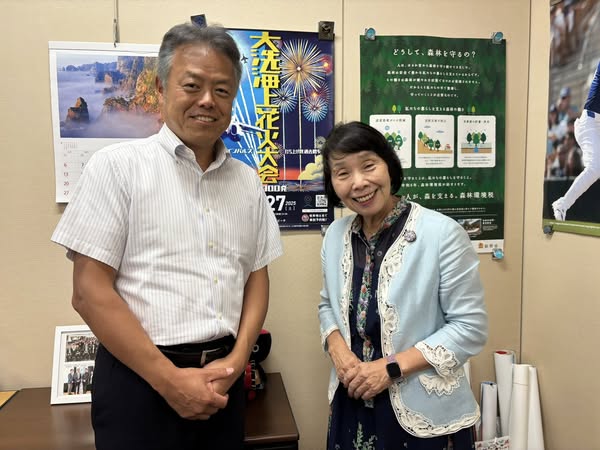総務省大臣官房審議官(税務担当)の福田毅さんとの出逢いは【幼児教育・保育の無償化】制度の構築の時
- 2025/08/17
- 日記・コラム, 訪問記録
- #総務省 #幼児教育保育の無償化 #地方消費税 #地方交付税 #地方財政計画 #休眠預金
令和元(2019)年 10 月1日から、安倍晋三総理大臣の時に、消費税増税のタイミングと同時にスタートしたのが、【幼児教育・保育の無償化】という新しい子育て支援制度です。
これは①子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図るといった少子化対策、②生涯にわたる人格形成の基礎やその後の義務教育の基礎を培う幼児教育・保育の重要性の観点から実施されているものです。
制度の内容は、幼稚園、保育園、認定こども園などの保育施設を利用する3歳から5歳まで(年少クラス~年長クラス)の子どもに対する保育利用料を無償化するというものです。
おもに3歳児から通うこととなる幼稚園についても、公立・私立問わず、無償化制度の対象となっています。
幼稚園の保育利用料は「通常保育」と「預かり保育」の2つに分類されており、それぞれ上限額が設定されているのが特徴です。
現時点では、【1号認定(通常保育)3~5歳児クラス】の場合は月額25,700円まで補助、【2・3号認定(預かり保育)3~5歳児クラス】は最大月額11,300円まで補助となります。
0~2歳児クラスは住民税非課税世帯のみ無償となります。
おもに共働き世帯の子どもが通う保育園については、認可、認可外、こども園などさまざまな種類があり、ほとんどの施設が無償化制度の対象となっています。
保育園においても幼稚園や認定こども園と同様、年少クラス以降の保育利用料が無償化となります。
それまでも、住民税の非課税世帯を中心に、無償化に向けた取り組みが段階的におこなわれてきましたが、この制度は所得制限がないため、基本的にどの世帯でも適用されるのが特徴です。
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
企業主導型保育事業の場合も、3歳から5歳までについては保育の必要性のあるこどもたち、0歳から2歳までについては住民税非課税世帯であって保育の必要性のあるこどもたちの利用料について、標準的な利用料が無償化されています。
この制度が導入されることが、平成30(2018)年6月15日の「経済財政運営と改革の基本方針2018」で閣議決定された際、私は三鷹市長在任中で、全国市長会の会長特命の【こども子育て施策担当副会長】を務めていました。
この閣議決定を受けて、同じ6月に全国市長会会長に就任された立谷秀清相馬市長を中心に、国とこの制度の最前線の自治体との対話の機会を持つことになりました。
当時の全国市長会社会文教委員会担当副会長であった三鷹市長の私と、前葉泰幸・津市長、谷畑英吾・湖南市長、こども子育て特別部会座長の泉房補・明石市長とで協議の場を持ちました。
さらに、【幼児教育の無償化に関する協議の場(通称:PDCA協議会)】で構成員は、内閣府特命担当大臣(少子化対策)・文部科学大臣・厚生労働大臣・全国知事会会長・全国市長会会長・全国町村会会長が組織されるとともに、【幼児教育の無償化に関する協議の場の幹事会】が設置され、知事会代表・市長会代表・町村会代表が実務的な協議を重ねました。
私は、幹事会の構成員を務めました。
さらに、【都道府県と市町村に関わる実務ワーキンググループ】及び【市町村実務検討チーム】が設置され、自治体での幼稚園・こども園・保育園等との実務が円滑に進むための協議も重ねられました。
私が幹事会のメンバーだったことから、三鷹市のこども政策担当職員がワーキンググループ、実務検討チームに参加させていただいていました。
一般に【無償化】と政策に名称が付くと、その財源のいっさいを国が保証するように聞こえます。
けれども、実際にはそうではありません。
そこで、無償化には自治体の歳出が増えることが懸念され、財源の国と自治体の負担の在り方が、大きな課題となりました。
私は、立谷・市長会長の特命を受けて、内閣府・文部科学省・厚生労働省の三省に加えて、総務省との協議を担当させていただきました。
その時に、総務省の当時の自治財政局長であった林崎理局長のもとで、対話を担当してくださったのが、当時の自治財政局調整課長であった福田毅さんだったのです。
たとえば、全国市長会のこども子育て特別部会に三府省の担当者と一緒に出席され、市長の意見を傾聴され、全国知事会・全国町村会の声も傾聴され、文字通り【調整】に力を尽くしていただき、次のような【幼児教育無償化に係る国・地方の負担割合の基本的な考え方】がまとめられていきました。
すなわち、【現行制度があるもの】については、今回の無償化の実現に当たっては、【現行制度の負担割合と同じ負担割合】とする。ただし、幼稚園(未移行園)に係る負担割合については、【国1/2、都道府県1/4、市町村1/4】とする。
実は、それまでの幼稚園(未移行園)に係る負担割合は【国1/3、市町村2/3】だったのです。
そして、【それ以外】については、幼児教育無償化の実施により、新たに無償化の対象となる認可外保育施設、預かり保育、ファミリー・サポート・センター事業等の負担割合について、子ども・子育て支援は全ての構成員が各々の役割を果たすことが求められるという子ども・子育て支援法の基本理念を踏まえ、【国1/2、都道府県1/4、市町村1/4】とする。
さらに、教育無償化に係る地方負担については、【地方財政計画の歳出に全額計上し、地方消費税、地方交付税などの一般財源総額を増額確保】する。
その上で、【地方交付税による財源調整を行い、個々の団体に必要な財源を確保】することになりました。
そうした重要な協議での出逢いがあった福田さんとは、2年前に内閣府の審議官(経済社会システム担当)・休眠預金等活用担当室長に就任されて、再会しました。
それは、私が4年前から今年の8月まで【内閣府休眠預金等活用審議会委員】をつとめていたことから、まさに、福田さんが担当室長になられたので、議員立法である休眠預金等活用法に基づく基本計画の5年目の見直しをご一緒に行うことができました。
審議会はコロナ禍を経て、原則としてオンラインで開催されてきましたが、私は時々内閣府を訪ねて、福田さんと歴代担当参事官とご一緒に対話をしてきました。
福田さんは、自治省に入省され、長野県、岩手県、茨城県での勤務を経験しながら、総務省・内閣府において、国と地方の関係の抜本的見直しを含む地方自治制度の再構築、消防や地方公務員に関する制度、人事・採用、マイナンバー関連のシステム構築、地方財政措置に関する調整、固定資産税課長など、実に様々な分野のお仕事をされてこられました。
7月に内閣府官房審議官から総務省官房審議官に異動された福田さんを、総務省官房審議官室に訪問すると、いつもと同じく爽やかな笑顔で歓迎してくださいました。
福田さんは茨城県総務部長をされていらしたご縁で、9月に開催予定の【大洗海上花火大会2025】のポスターが貼ってありました。
また、長野県でもおつとめでしたので、三鷹市と友好都市の川上村はじめ長野県にも時々訪問されるそうです。
私が三鷹市長時代に大変にご厚誼いただいた全国町村会の会長も務められた川上村の藤原忠彦前村長ともご縁があるとのことで、本当に心強いと思いました。
【幼児教育・保育の無償化】という新しいこども子育て支援施策は、現在は私が参与を務めている【こども家庭庁】が所管していますが、地方財政の状況を踏まえると、総務省の政策との連携は不可欠であると思います。
改めて、制度を産み出す際の林崎自治財政局長、福田調整課長はじめ総務省と三府省及び自治体との連携の意義を再確認しています。
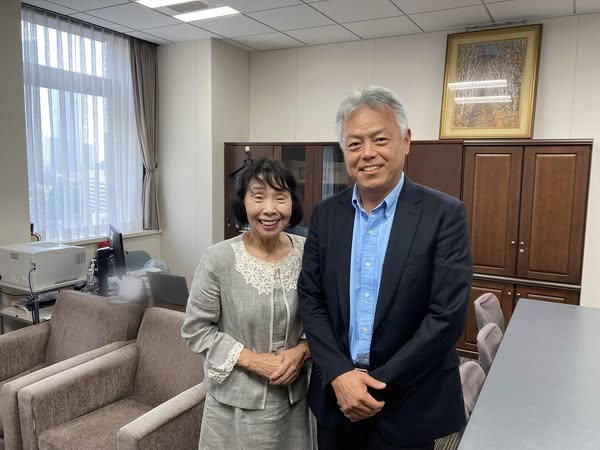
 清原慶子 Official Website
清原慶子 Official Website