【障がいのあるこどもを含むすべてのこどもの教育課程の充実を目指して】
【学習指導要領】とは文部科学省が学校教育法等に基づき、小学校・中学校・義務教育学校(前期課程・後期課程)・高等学校・中等教育学校(前期課程・後期課程)・特別支援学校(小学部・中学部・高等部)で、各教科の教育課程を編成する際の基準を定めるもので、国立学校・公立学校・私立学校を問わずに適用されます。
これは、全国のどの地域のどの学校で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるために定められるものであり、校種ごとにそれぞれの教科等の目標や大まかな教育内容を定めています。
【学習指導要領】は、国際情勢の変化や社会の要請などに応じて、おおむね10年に1度改訂されています。
現行の【学習指導要領】は、小・中学校については2017年度、高校については2018年度に改訂が告示され、小学校は2020年度から全面実施されています。
移行が最も遅い高等学校では2024年度から全学年での完全実施が行われています。
次期学習指導要領については、中央教育審議会において、2024年12月の文部科学大臣による諮問を受け、【教育課程企画特別部会】が設置され、初等中等教育分科会や教育課程部会への報告を交えつつ、教育課程の枠組みに関する事項や教科横断的な事項を中心として審議が行われてきました。
そして、9月25日に、12回にわたる検討の結果が暫定的に取りまとめられ、今後の特別部会における更なる検討の深化や各ワーキンググループ等での検討の前提として、【次期学習指導要領に向けた基本的な考え方】がとりまとめられています。
その内容は、生涯にわたって主体的に学び続け、多様な他者と協働しながら、自らの人生を舵取りすることができる、民主的で持続可能な社会の創り手を「みんな」で育むため、
①「主体的・対話的で深い学び」の実装(Excellence)
②多様性の包摂(Equity)
③実現可能性の確保(Feasibility)
の3つの方向性を踏まえて議論を行うこととされています。
これらの3つの方向性に基づく改善は、教育課程内外のあらゆる方策を用いつつ、三位一体で具現化されるべきもの提起されています。
私は今年の3月から【第13期中央教育審議会】 の委員を務めていますが、この9月に文部科学大臣から【初等中等教育分科会】への配属が任命され、10月9日に【中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会】に設置された【特別支援教育ワーキンググループ】の第1回の会議が開催され、委員として出席しました。
そして、教育課程部会の奈須正裕(上智大学総合人間科学部教授)部会長のご指名で私が【主査】に、奥住委員が主査代理に指名されました。
事務局から、私については、東京都三鷹市長を4期16年務めた他、内閣府「障害者政策委員会」や厚生労働省「社会保障審議会障害者部会」、文部科学省が2019年に設置した「中央教育審議会 初等中等教育分科会 特別支援教育の在り方に関する特別委員会」の委員等を務めたことなどが紹介され、奥住委員については、文部科学省が2022年に設置した有識者会議「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議」において副座長を務められたこと、この度教育課程部会の下に設置した「総則・評価特別部会」にも御参画いただくこととなっていることが紹介されました。
【特別支援教育ワーキンググループ】の委員は下記の皆様です。(敬称略)
・青山新吾:ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科准教授・インクルーシブ教育研究センター長
・足羽英樹:鳥取県教育委員会教育長
・有吉万里矢:全国肢体不自由特別支援学校PTA 連合会会長
・一木薫:福岡教育大学教育学部教授
・海老沢穣:一般社団法人 SOZO.Perspective 代表理事
・大関浩仁:東京都品川区立第一日野小学校校長、全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会会長
・緒方直彦:東京都立あきる野学園統括校長、全国特別支援学校長会会長
・奥住秀之:東京学芸大学特別支援科学講座教授
・亀田香利:能美市教育委員会事務局次長兼学校支援課長
・川合紀宗:広島大学ダイバーシティ&インクルージョン推進機構マネジメント部門長・ウェルビーイング推進室長・教授
・菊地一文:弘前大学大学院教育学研究科教職実践専攻教授
・清原慶子:杏林大学客員教授、前東京都三鷹市長
・是永かな子:高知大学教育研究部人文社会科学系教育学部門教授
・澤隆史:東京学芸大学教育学部教授
・谷口明子:東洋大学文学部教育学科教授
・丹治敬之:筑波大学人間系准教授
・野口晃菜:一般社団法人 UNIVA 理事
・堀川淳子:広島市教育委員会事務局学校教育部特別支援教育課長
・宮内久絵:筑波大学人間系准教授
このWGの会議は頻繁に開催されることもあり、原則として、主査・主査代理以外は、オンラインで会議に参加していただくことになっています。
この日は、奥住主査代理に加えて、会議の前に足羽委員が【令和7年度地方教育行政功労者表彰(文部科学大臣表彰)】を文部科学省講堂で受章されたことから、会議室で参加されてお慶びを申し上げることができました。
会議の冒頭に、今村聡子・大臣官房文部科学戦略官が、【次期学習指導要領に向けた基本的な考え方】で示された3つの方向性を踏まえつつ、特別支援教育の実態を踏まえた課題解決に向けて闊達な意見交換をしていただきたいと挨拶をされました。
その後、酒井啓至・特別支援教育企画官による、教育課程企画特別部会論点整理・「こども若者★いけんぷらす」における特別支援学校等の子供たちからの意見・特別支援教育に関する現状・課題と検討事項の概要を報告を受けました。
その報告を踏まえつつ、WGの初回であることもあり、委員の皆様全員に、WGに求められている【今後の検討事項】等に関する御意見を発言していただきました。
委員の皆様は、多様な障がい種別をご専門とされる専門家の皆様、教育現場の実践も経験されているとともに自治体の教育行政に携わっている皆様です。
そこで、ご意見は多岐にわたりましたが、各委員の特別支援教育の必要性と現在の課題を踏まえて、より適切な在り方を提起していきたいとの共通の熱意を感じました。
具体的には【次期学習指導要領の基本的な考え方】に【多様性の包摂】が含められたことの意義、【社会モデル】の意義、【基礎的環境整備と合理的配慮の具体化】【自立活動の意義とその具体化】【通級による指導の充実】【インクルーシブ教育の在り方】【すべての教員に特別支援教育への理解の必要性と養成・研修・支援の在り方】など、重要な視点・論点が提起されました。
私は、文部科学省の担当者が、こども家庭庁と連携して、【こども若者★いけんぷらす】における特別支援学校等のこどもたちからの意見を聴いていることを心強く思います。
当事者の声を傾聴することで課題解決が図られると思います。
会議には、今村戦略官、酒井企画官の他に、武藤教育課程課長、栗山教育課程企画室長、生方特別支援教育課長、堀江課長補佐、梶課長補佐、菅野視学官、松岡調査官、村上調査官、加藤調査官、深草調査官、近藤調査官、清重特別支援教育総合研究所理事、佐藤指導係長はじめ、多数の事務局の皆様が参加してくださいました。
そこで、会議後に、この日会議室で参加した奥住主査代理、足羽委員と私は、オンラインで参加してくださる委員の皆様の想いを添えて、このWGを支えていただく事務局の皆様と今後の取組みの充実に向けてよい【チームワーク】で臨んでいきましょうとの決意を共有しました。
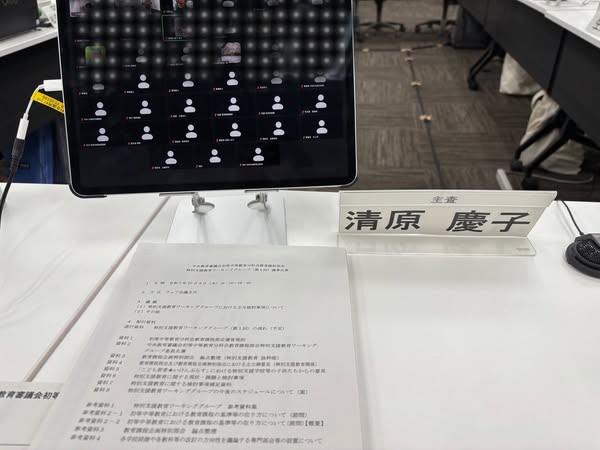
 清原慶子 Official Website
清原慶子 Official Website




