【地域コミュニティにおけるNPO法人の活躍と社会教育】
- 2025/09/09
- 日記・コラム, 審議会・委員会等
- 社会教育, 生涯学習, 民間公益団体, NPO法人, 特定非営利法人, ふくおかNPOセンター, NPO法人みらいずworks, 社会教育士
私は、文部科学省中央教育審議会生涯学習分科会長を務めています。
そして、昨年6月の文部科学大臣からの諮問【地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方と推進方策について】を受けて、分科会の中に【社会教育の在り方に関する特別部会】を設置して、その部会長も務めています。
特別部会は2024年8月に第1回の会議を開催して以来、9月には第 10回の会議を開催しました。
【地域コミュニティの基盤を支える今後の社会教育の在り方と推進方策について】の諮問に示されている【主な審議事項】は、【①社会教育人材を中核とした社会教育の推進方策】【②社会教育活動の推進方策】【③国・地方公共団体における社会教育の推進体制等の在り方】の3点です。
そこで、特別部会では、【①社会教育人材を中核とした社会教育の推進方策】についての検討から開始して、今年の3月に【審議事項1に関する意見の整理】をまとめました。
その後、5月以降の会議では、【②社会教育活動の推進方策】についての審議を重ねています。
【②社会教育活動の推進方策】については、大変に幅広い内容を含んでいます。
たとえば、地域と学校の連携・協働の更なる推進方策、公民館、図書館、博物館等における社会教育活動の推進方策、青少年教育施設等における青少年体験活動の推進方策、地域コミュニティに関する首長部局の施策や多様な主体が担う活動との連携・振興
方策、共生社会の実現に向けた障害者・外国人等を含めた社会教育の推進方策等です。
第10回の会議では、諮問理由の記載にある【地域コミュニティに関する首長部局の施策や多様な主体が担う活動との連携・振興方策、特に、環境・福祉・防災・農山漁村振興・まちづくり等の多様な分野における行政機関や高等教育機関、民間公益活動を含む関係団体や民間企業等による取組に対し、社会教育が連携・貢献しうる観点からの検討】を行うことにしました。
そこで、特に【民間公益活動と社会教育の連携】に焦点を当てて、委員である特定非営利活動法人ふくおかNPOセンター代表理事の古賀桃子さんと、NPO法人みらいずworks代表理事の小見まいこさんに報告していただきました。
古賀委員は【社会教育×NPO― 課題解決と学びを両立するエコシステム構築に向けて】と題して、ふくおかNPOセンター関連の教育(生涯学習・青少年教育)の取り組みを踏まえて、【民間公益活動を含む関係団体による取組に対し、社会教育はどのような観点から連携・貢献できると考えられるか】という問いかけに、3つの視点を提起されました。
すなわち、①越境(分野・エリア・世代)の促進役、②実践者兼伴走者(プレイング・コーディネーター)、③個々人の学びのモチベーター、の3点です。
小見委員は、【NPOの活動と社会教育の連携】と題して、NPO法人みらいずworksの【キャリア教育】【探求学習】【対話の場】【教職員研修】【多分野連携】の実践を踏まえて、地域コミュニティにかかるNPOの共通課題を①人材不足と担い手の偏在、②社会的認知の低さによる収益性の困難さ、③地域課題の多様化・複雑化を提起されました。
そのうえで、①コミュニティ・スクールに係る継続的な研修の企画・運営の実践事例からは、【教職員に社会教育の視点があると協働が進みやすいこと】を提起され、②子どもたちの意見表明・社会参画の仕組みづくりの実践事例からは、【その調整役(コーディネート)は、社会教育行政や社会教育人材が担えること】を提起されました。
お2人の実践に基づく問題提起を参考に、その後、委員の皆様それぞれから、さらに具体的な実践事例に基づく、地域コミュニティにおけるNPO法人の活動と首長部局及び教育委員会との連携・協働の意義と課題が確認されました。
会議の最後に本特別部会のもとに、【社会教育主事・社会教育士養成等の改善・充実に関するワーキング・グループ】の設置が承認されました。
これは、前期に設置された【社会教育人材部会】の最終まとめ及び、今期の【審議事項1(社会教育人材を中核とした社会教育の推進方策)に関する意見の整理】を踏まえて、社会教育主事・社会教育士養成に関するさらに具体的な検討と提案が必要と考えたからです。
この日のNPO法人での実践事例に基づく委員の皆様による意見交換からも、初等中等教育・高等教育・社会教育の分野を超えた連携・協働が必要であること、古賀委員の使用された用語を使うならば【越境】が必要であることが確認されたように思います。

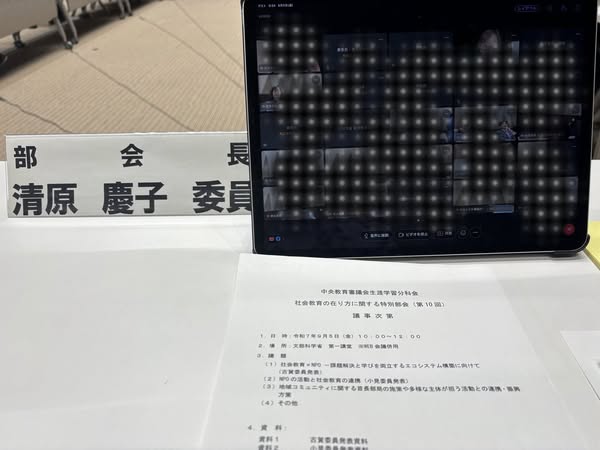
 清原慶子 Official Website
清原慶子 Official Website




