【総務省統計委員会第7回デジタル部会】に参加し、再確認する【デジタル化】と【統計】の関係の重要性
9月12日に総務省統計委員会【デジタル部会】が会議室とオンラインによるハイブリッド方式で開催され、私は部会長として出席し、会議の進行役を務めました。
【デジタル部会】は、第9期の統計委員会が発足した2023年10月に設置が決定しました。
その根拠は、2023年3月に閣議決定された【第Ⅳ期公的統計の整備に関する基本的な計画】にあります。
この計画には、「デジタル経済の実態把握」、「報告者の負担軽減及びユーザーの利便性向上」、「統計作成の効率化及び正確性向上」など、様々な観点からの各種施策を定めています 。
これらの課題をデジタル化の視点から検討する必要性を認識し、統計委員会において【公的統計のデジタル分野全般を取り扱う】ことを目的とした【デジタル部会】が設置されたのです。
委員は以下の8名です。(敬称略)
〇委員:清原慶子(杏林大学客員教授)會田雅人(滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター特任教授)
〇臨時委員:小西葉子(筑波大学システム情報系教授・独立行政法人経済産業研究所上席研究員;特任)中川郁夫(株式会社ソシオラボ代表取締役)
〇専門委員:竹村詠美(Peatix Inc. 共同創設者・アドバイザー)細川努(総務省デジタル統括アドバイザー)南和宏(統計数理研究所学際統計数理研究系教授)安井清一(東京理科大学創域理工学部経営システム工学科准教授)
また、第7回会議の総務省事務局の出席者は以下の通りです。(敬称略)
〇総務省事務局:北川修(政策統括官)・阿南哲也(大臣官房審議官)・北原久(国際統計交渉官)・谷本信賢(統計委員会担当室長)・赤谷俊彦(統計委員会担当室次長)・松井竜介(統計委員会担当室政策企画調査官)齋藤恵一(同室長補佐)・孕石真浩(同室専門官)
部会の審議は2024年3月4日の第1回以降、おおむね3か月に1度の会議を重ねて、公的統計のデジタル分野全般に関わる幅広い内容を対象にしつつも、主として【統計の対象としてのデジタル経済・社会】及び【統計調査のデジタル化】を柱に審議を行い、議論を深めてきました。
そして、各回の議事概要については、統計委員会の定例会議で必ず報告し、委員の皆様から質疑や応援をいただいてきました。
そして、9月12日で7回目を数えました。
今期の統計委員会の任期が10月中旬となることから、この日は今期の最終回と位置づけ、【デジタル部会(第1回~第7回)の審議内容の整理・取りまとめ(案)】について、以下の構成案に基づき審議しました。
第1章 本文書の背景及び目的
第2章 統計の対象としてのデジタル化
2-1 デジタル経済に関する既存の公的統計と整備に向けた取組
2-2 デジタル経済の統計的把握に向けた課題
2-3 中長期的な展望
第3章 統計調査のデジタル化
3-1 これまでの各府省庁における取組
3-2 中長期的な展望
第4章 今後の部会審議に向けて
4-1 生成AIに着目した検討
4-2 デジタル化の社会への影響を幅広く捉えた議論
4-3 諸外国及び国際機関におけるデジタル化に関する統計についての継続的な調査研究実施の必要性
統計委員会に設置されている部会のほとんどは、総務大臣からの諮問に基づく審議を中心としていますが、デジタル部会は諮問についての審議をする部会ではありません。
そこで、毎回、ゲストの講演や事務局の報告について委員の皆様による活発な意見交換が行われてきました。
たとえば、【統計の対象としてのデジタル化】の表現について、【統計の対象としてのデジタル経済・デジタル社会】というように、広義に取り組んだことの意義の再確認がありました。
また、改めて、統計のデジタル化については、【統計委員会は各府省庁による統計調査のデジタル化に向けて引き続き協力又は支援する】ことの意義が再確認されました。
さらに、今後の展望として、急速に技術革新が進み、利活用の範囲も拡大してきている【生成AI】の統計分野における適切な利用についても共通認識を持ちました。
私は地域情報化、電子政府等情報通信政策に関する研究者として、市民の皆様・職員の皆様と国勢調査をはじめとする公的統計調査を担ってきた市長経験者として、【デジタル部会】の意義を強く認識しています。
そして、【デジタル部会】の部会長として、審議の地平を委員の皆様、総務省事務局の皆様と協働して切りひらいてきたことを誇りに思います。
7回目の会議の終わりに、第9期の節目を迎えて、会議室で参加した委員の皆様、事務局の皆様と記念写真を撮影しました。
社会経済、教育や生活の各分野におけるデジタル化が進む中にあって、【デジタル部会】は、引き続き、総務省統計委員会において、重要な役割を果たすことを確信しています。
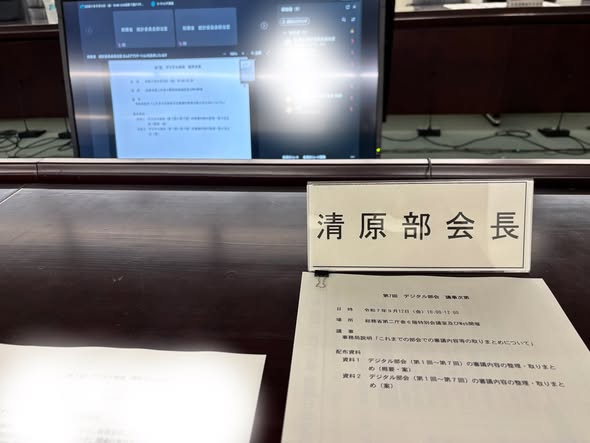
 清原慶子 Official Website
清原慶子 Official Website




