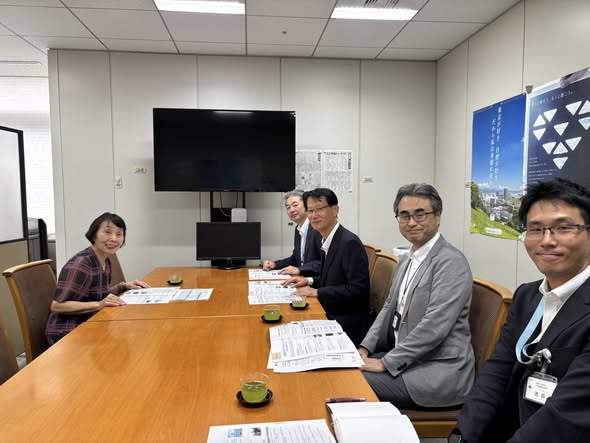【東京都の佐藤総務局長、石橋次長らと語り合った大学院で学ぶことの意義と支援の必要性】
私は、慶應義塾大学法学部政治学科の卒業を控えて、進路を悩んだ末に、一般企業等への就職ではなく、大学院に進学したいと決意しました。
そのきっかけを与えてくださったのは、当時2年生から開始されていたゼミナール(研究会)で指導を受けていた教授と、教授を補佐して支えてくださった助手やティーチングアシスタント(TA)を務めていただいた複数の大学院生の存在でした。
TAの皆さんはサブゼミ等で指導してくださるとともに、大学院での学びについても情報提供をしてくださいました。
そこで、私は大学の4年間だけでは学び足りないとの想いと、進路の選択肢に大学院進学があることを知ったのです。
ただ、私が大学4年生の1970年代は、法学部政治学科の学生のほとんどは男子でした。
2023年度の女子の大学進学率は54.5%で、過去最高の伸びを示しましたが、私が大学を入学する1970年当時の女子の大学進学率はようやく10%を超える程度でした。
しかも、女子の大学院への進学率はさらに低かったことから、私はまず両親に相談しました。
すると、父が、私に次のように話してくれました。
「実は、私は次男であったので10代で満州(中国東北部)に渡り働いていたところ、19歳で徴兵を受けて出兵して、終戦後は幸いにも無事に帰国できました。そして、結婚をした時、妻である慶子のお母さんがこれからは学問が必要になるからと大学進学を勧めてくれました。妻は助産師で助産所を開業して自分を支えてくれて、自分も働きながら大学に通いました。そして、4年生を迎えた時指導教授から大学院進学を勧められました。ところがちょうどその時、お母さんの妊娠がわかったので、進学を諦めたのです。だから、慶子が、今、大学院へ行きたいというなら、絶対に応援するから、とにかく勉強はできるときにしなさい」と。
さらに、私は幸いにも、【大学院修士課程】進学の【推薦】を受けることになり、学力試験は免除され、意思確認の面接のみで進学することができました。
その後、修士課程に進むと同期の女子は私1人でしたが、指導教授とともにそれ以外の教員の皆様も、同期の仲間も、先輩の皆様も応援してくれて、私は博士課程に進学する決意をしました。
受験科目には、英語・フランス語・専門科目がありましたが、どうにか無事に合格して学びを続けることができました。
けれども、学業に専念するためには、一定の時間と高額の書籍等を購入する費用がかかることから、博士課程在学中の3年間は日本育英会の奨学金の貸与を申請し、大いに助かりました。
その後、必要単位を取得して3年で退学した後の4年間のオーバードクター時代は、日本学術振興会の奨励研究員に採用していただいて、研究を継続し、論文を執筆したり、学会で発表することができました。
そして、4年後の31歳の時に、新設大学の専任教員として採用していただくことができました。
2025年2月に私が属する文部科学省中央教育審議会から答申された【我が国の「知の総和」向上の未来像 ~高等教育システムの再構築~】でも、【大学院教育の改革】【研究力の強化】が提起されていて、私もこれらは重要な課題であると思っています。
その答申後の2025年6月に、東京都立大学は、「2025年度より、同学に在学中の博士後期課程学生に対し、新しい支援プロジェクトとして【みやこMIRAI(Motivating Integrated young Researchers towards Adaptive intelligence Initiative)プロジェクト】を開始することを公表しました。
私は、その内容について、詳しくお話をお聴きしたいと思い、都立大学を所管されている東京都の佐藤智英・総務局長、石橋浩一・総務局次長を訪問した際に、【みやこMIRAIプロジェクト】について、教えていただきました。
佐藤局長は栗原大・総務局都立大学調整担当部長と池田拓也・総務局大学調整担当課長を同席され、本プロジェクトの内容をはじめ成人を対象にした【プレミアム・カレッジ】についても説明をしてくださいました。
この【みやこMIRAIプロジェクト】では、一定の資格要件(日本国籍を有する者、特別永住者等で、入学時30歳未満、標準修業年限内などを満たす学生)の全員を対象に、生活費相当額(月額20万円:年額240万円)を支給するとともに、授業料(年額52万円程度)の免除等の支援を行うことで、研究に専念できる環境を提供するものです。
また、メンターによる面談、研究インターンシップ等のキャリア支援も実施するとのことです。
さらに、研究業績の優れた学生(独立行政法人日本学術振興会特別研究員〈DC1及びDC2〉、東京都立大学領域リフレーミング〈Arena Reframing: AR〉双対型博士人材育成プロジェクト(SPRING)等の採用学生及び同等と認められた学生)に対しては、2年次以降給付額を上乗せすることで、授業料免除と合わせて同世代の社会人の給与と同水準の支援を行うとのことです。
このプロジェクトの発表の際、大橋隆哉・東京都立大学学長は、
「本学は、日本の研究力が低下することへの危機感から、学生のこうした不安に寄り添い、研究に専念できる環境を整備するため、これまで博士後期課程学生への様々な支援に取り組んできました。
令和7(2025)年度より、本支援プロジェクトを立ち上げ、博士後期課程へ進学する学生への経済的支援を大幅に増額し、安心して学問に集中できる環境を整えます。これにより意欲ある学生が切磋琢磨しつつ成長していくことを後押しし、研究力だけでなく卓越したコミュニケーション力と主体性にも支えられ、世界の幅広い分野で活躍できる次世代の高度専門人材を育ててまいります。
ぜひ本学で学問の奥深さとともに社会へ関わっていく面白さを体験し、変化する世界へ飛び出していってください。」とコメントを発表しています。
都立大学は、併せて、【海外留学支援】についても2025年度から拡充するとしていて、留学期間、留学先、成績及び世帯年収に応じて渡航費・滞在費等を支援するとのことです。
国内外の物価高騰を受けて、留学を断念するお話を聴くことも増えていることから、このような支援が留学希望を全うする大きな支援になると想定します。
私が大学院で学んでいた当時は、もちろん都立大学にもこのような支援体制はありませんでしたが、現代は、本プロジェクトを通じて、優秀な人材の博士後期課程への進学を促進することになると受け止めます。
次世代を担う研究者を育成することは、大学教員を育成することにもなりますし、民間の研究機関や企業の研究所等でも科学技術分野を含む多様なキャリアパスの支援になると思います。
日本における大学進学率は諸外国に比べて相対的に高い水準にありますが、大学院への進学については、引き続き、志願者の決意を妨げる経済的・社会的・心理的障壁があることも事実です。
私は、22歳で大学を卒業するとき、当時の状況では、自分自身の人生の未来の【ライフデザイン】を描きにくくさせる大学院進学を選択しました。
案の定、就職も、結婚も、30歳を過ぎてからになりました。
出産も33歳と37歳と、当時としては遅くなりました。
けれども、70代を迎えた今、大学教員としても、三鷹市長としても、今の多様な活動分野においても、自身が大学・大学院で学んだことや、その過程で巡り合った多くの恩師や研究仲間によるヒューマン・ネットワークから、多くの【賜物】をいただいてきたことを痛感します。
全ての人が大学院に進学する必要はもちろんありません。
けれども、社会においては、大学院での学びや調査研究等を通して、幅広い研究分野での研究の進化を担い、社会に貢献する人財は、必ず必要です。
公立大学の1つである、東京都立大学が【研究力だけでなく卓越したコミュニケーション力と主体性にも支えられ、世界の幅広い分野で活躍できる次世代の高度専門人材の育成】を目指して、一定の経済支援の決断をしたことが、有効な成果を挙げることを心から期待したいと思います。
今度、ぜひ東京都立大学のキャンパスを訪問したいと思います。
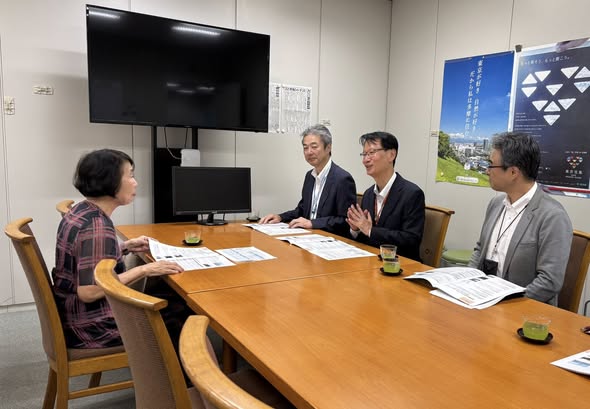


 清原慶子 Official Website
清原慶子 Official Website