【地域コミュニティにおける企業・大学・NPOなど多様な主体の連携による学びと活動の場の充実を】
10月7日、文部科学省中央教育審議会生涯学習分科会【社会教育の在り方に関する特別部会(第 11 回)】に部会長として参加しました。
本会議は、対面とオンラインを併用して開催されており、私は文科省の会議室で参加しました。
この特別部会は、2024年6月に文部科学大臣から諮問された【地域コミュニティの基盤としての社会教育の在り方】についての審議を行うために設置されたものであり、この日はこの諮問における審議事項2【社会教育活動の推進方策】のうちの4つ目の課題である【地域コミュニティに関する首長部局の施策や多様な主体が担う活動との連携・振興方策】について、意見交換しました。
前回は、NPO法人等民間活動団体の事例から考察しました。
この日は、課題についての意見交換の充実を目指して、最初に、金澤義明委員(明治安田生命保険相互会社執行役員・地域リレーション推進部長)から、【明治安田の地域貢献について】と題して、企業の地域貢献の事例を通して、地域コミュニティの基盤としての社会教育への期待を提起していただきました。
金澤さんは、【明治安田フィロソフィー】とは、【お客様に「確かな安心を、いつまでも」をお届けすることを使命に、お客さま・地域社会・働く仲間との絆を大切に「人に一番やさしい生命保険会社をめざす】ことだと紹介されました。
この理念に基づき、【みんなの健活プロジェクト】【地元の元気プロジェクト】を進めています。
具体的には、2025年3月31日時点で1,078(市区町村1,034、都道府県44)の自治体と連携協定を締結して、この連携協定をもとに、行政サービス案内活動の展開・社会課題の解決などの取組みを推進してるとのことです。
また、サッカーの60のJクラブとの協働イベントを行ったり、公益社団法人全国公民館連合会と「地域コミュニティの持続的な発展」をテーマとした活動を進めています。
「地元の『公民館』元気プロジェクト」を共同で推進。公民館・民間企業等との幅広い連携・協働
こうした実践に基づき、民間企業の視点から社会教育との連携にあたっての提案として、自治体参画の見える化・認定制度の創設・企業の協業促進の3点を提起されました。
次に、高等教育局大学振興課の石橋晶課長より【地域大学振興の取組の推進~地域コミュニティの基盤を支える社会教育に対する期待】について報告がありました。
まず、文部科学省の事業として2013年度より開始された「地(知)の拠点整備事業(COC)」は、地域社会と連携し、全学的に地域を志向した教育・研究・地域貢献を進める「地域のための大学」として、地域の課題(ニーズ)と大学の資源(シーズ)をの効果的なマッチングにより地域課題解決、さらには地域社会と大学が共同して地域課題を共有し、それを踏まえた地域振興策の立案・実施までを目指した取組を推進してきた経過を紹介しました。
次に、今年の2月に提出された、中央教育審議会の今後の高等教育政策の方向性と具体的方策を示した、いわゆる【知の総和答申】について紹介しました。
その中で、社会教育との関係では、教育研究の「質」の更なる高度化のために、【高等教育のアクセス確保】とりわけ【地域のアクセス確保・人材育成のための協議体構築】が不可欠として【地域構想推進プラットフォーム(仮称)】が提起されたことを紹介しました。
これは、地域の高等教育機関、地方公共団体、産業界など関係者が議論する協議体の構築であり、各地域の地域アクセス確保・人材育成等の状況を踏まえ、国と連携した多様なモデルを展開する見込みです。
これは、いわゆる【産官学金労言】等地域の多様な関係者の関わり・情報共有、多様な財源マネジメント等が可能な連携基盤の構築を促進しようとするものです。
そこで、各地域の生活・産業基盤を踏まえた各大学等が果たす役割の認識共有、高校等や地域産業界等と連携した一体的な取組の推進が求められます。
石橋課長は、文部科学省では2025年4月より高等教育局大学振興課内に【地域大学振興室】を設置して、司令塔機能を強化していることを紹介しました。
そして、【地域大学振興に関する有識者会議】を設置して、有識者の他に、【特別委員】として現役の大学生6名に参加してもらい、【令和8年度地域大学振興プラン(仮称)】を検討した経過から、【地域コミュニティの基盤を支える社会教育に対する期待】として、【魅力ある地域の学びの場の整備】を挙げました。
すなわち、地域での高校・大学における充実した学びの経験が進路・就職先選択に影響を与えていることから、【地域での学びの場】が魅力的なものとなるよう、社会教育主事が地域の生活・産業基盤やコミュニティを支える担当部局との連携を充実させることが期待されると語ります。
それとともに、具体化には、社会教育主事のみならず、社会教育士や地域学校協働活動推進員など社会教育の専門性を有する人々が、地域の産業界を含む地域関係者や、大学をはじめ地域の教育機関と連携し、そのニーズも踏まえながら整備することが期待されると話しました。
お2人の報告を契機として、委員の皆様の意見交換を通して、さまざまな企業のCSR(Corporate Social Responsibility)活動が行われてきている現状を踏まえて、今後、人口減少や人手不足といった状況がある中、企業の地域貢献活動の更なる活性化や社会教育との連携の重要性が確認されました。
私も金澤委員に質問させていただいて、社員の皆様にとっても地域活動への参画を通して、有意義な影響があることを確認しました。
また、大学等の高等教育機関は、各地域の【知の拠点】として、地域課題の解決への貢献や地域に根差した人材育成等が期待されていますが、それは教員のみならず、学生の活動とも密接に連携していることも確認されました。
一方で、大学は社会教育人材の養成課程をもっているわけですが、その課程を担当できる教員不足や大学経営の実情から、その維持が困難になっている現状も共有されました。
また、事務局の髙田地域学習推進課長から、文部科学省からの要望事項であり決定事項ではないとのお断りの上で、【地元企業の地域学校協働活動への参画促進に向けた法人税の税額控除の創設】【民間企業の従業員が学校教育活動の指導者として活躍するモデル】が紹介されました。
まずは、企業の地域学校協働活動への参画の促進に向けて、税制面での配慮が検討されていることは新しい政策の方向性であると思います。
地域コミュニティの学びの場の充実に向けて、企業、大学、NPO法人等幅広い活躍が期待されます。


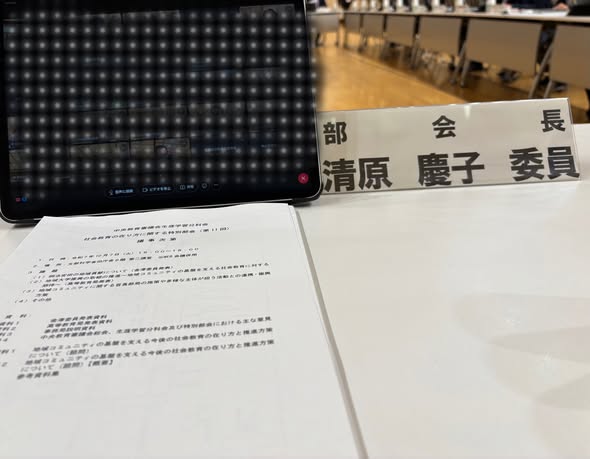
 清原慶子 Official Website
清原慶子 Official Website




