【第143回中央教育審議会総会】で意見を述べました
- 2025/10/25
- 日記・コラム, 審議会・委員会等
- 文部科学省, 中央教育審議会, 初等中等教育, 教育課程, 学習指導要領, 多様性の包摂, 教員.給特法, 学校における働き方改革, コミュニティスクール, 学校運営協議会
第143回中央教育審議会総会がハイブリッド形式で開催され、私は文部科学省旧館の講堂で会議に出席しました。
10月21日に新内閣がスタートし、文部科学大臣に松本洋平衆議院議員が就任されました。
この日の総会には、中村裕之(なかむらひろゆき)文部科学副大臣(衆議院議員)と福田かおる文部科学大臣政務官が出席されました。
中村副大臣は、2019年文部科学大臣政務官にご在任中に【GIGAスクール構想】を提案され1人1台端末を実現されたこと、衆議院文部科学委員長として【給特法】の改正を担当したことを紹介されました。
そして、教員志願者が少なくなる中、教員志望者にとって望ましい働き方改革を進めていきたいと話されるとともに、いじめ・不登校等についての検討を期待すると挨拶されました。
福田大臣政務官は、お父様が教育学者でお母様が小学校教員でいらっしゃることから、教育には特に関心を持たれていたことを紹介され、社会や技術の急速な変化の中、学びの継続がしやすい環境づくりをと提起されました。
この日の議題は以下の3件です。
(1)初等中等教育における教育課程の基準等の在り方に関する論点整理について
(2)多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策に関する論点整理について
(3)公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の成立等について
いずれも、事務局は文部科学省初等中等教育局で、【議題1 初等中等教育における教育課程の基準等の在り方に関する論点整理】について、は望月禎(もちづきただし)初等中等教育局長が説明されました。
その説明を受けて、10名を超す委員の皆さんが意見を述べました。
私は、次の3点について意見を述べました。
【1】第1章【次期学習指導要領に向けた検討の基盤となる考え方】は【主体的・対話的で深い学びの実装】【多様性の包摂】【実現可能性の確保】の3つが提示されている中、特に、【多様性の包摂】については、私が主査を務める【教育課程部会特別支援教育ワーキンググループ】の会議において、その意義を評価するとのご意見が多くあり、今後、その意義を踏まえながらワーキンググループでの審議を丁寧に進めていきたい。
【2】第2章質の高い、深い学びを実現し、分かりやすく使いやすい学習指導要領の在り方について、①構造化に続いて、②表形式化、③デジタル化が示されている点は重要。
また、【デジタル学習基盤を前提とした学びの在り方・学習指導要領と「個別最適な学びと協働的な学び」の関係の在り方】が示されていることは、GIGAスクールが開始され、授業にタブレット等のデジタル化が進んでいる学校の現場を踏まえた、現実的な方向性の提起と受け止める。生成AIの適切な活用を図るとともに、人間ならではの能力を研ぎ澄ませていく授業や学校での活動について、学習指導要領についての教職員の理解と創意工夫をはかる条件整備が必要である。
【3】第3章多様なこどもたちを包摂する柔軟な教育課程の在り方について、多様な子供たちを包摂できる教育課程の実現に向け、標準授業時数の弾力化を可能とする「調整授業時数制度」の導入等柔軟性が提起されているところ、それを実現するために【カリキュラムマネジメント】が重要性を増すことから、そのための研修等の充実を図る必要がある。
【議題2:多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策に関する論点整理】については、堀野晶三・学習基盤審議官が説明をされました。
「教師⼈材の質の向上と⼊職経路の拡幅を強⼒に推進し、多様な専⾨性を有する質の⾼い教職員集団の形成を加速することが必要」とのことから、①社会の変化や学習指導要領の改訂等も ① ⾒据えた教職課程の在り⽅、②教師の質を維持・向上させるための採⽤・研修の在り⽅、③多様な専⾨性や背景を有する社会⼈等が教職へ参⼊しやすくなるような制度の在り⽅について、教員養成部会の審議を踏まえた論点が示されています。
私は、特に、論点③に提起されていた「⼤学院段階における教職課程の在り⽅について、多様な学部出⾝者や社会⼈経験者が新しいプログラムを履修することによって標準的なレベルの免許状を取得できるような仕組みを考えていく必要」との指摘は重要であり、その具体化への期待を述べました。
というのは、私は、大学院の博士課程において教職課程を学部の学生と一緒に履修し、高校での教育実習を経験して中学校社会・高等学校社会の免許を取得しましたが、大学院生が教育実習に行くことが生徒に一定のロールモデルを提起することにもなり、相互に意義があったとの実体験があるからです。
本議題についても、多くの委員が意見を表明されました。
【議題3公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の概要】についても、堀野晶三・学習基盤審議官が説明をされました。
私は、第1期の【学校における働き方改革に関する特別部会】のメンバーとして【教職調整額の基準となる額の引上げ】は課題となったいたことから、それを含む給特法の改正は有意義であるところ、それを実現するために、「公立学校の校長が学校運営協議会の承認を得ることとなっている学校運営に関する【基本的な方針】に、業務量管理・健康確保措置の実施に関する内容を含める。」という法の内容が参議院文教科学委員会の付帯決議の11番目に「業務量管理・健康確保措置の実施における学校運営協議会の役割の重要性に鑑み、学校運営協議会の設置を推進するとともに、学校運営の支援機能向上、学校運営協議会委員の研修の改善と適切な処遇を行うこと。」とされていることも重要であると考えます。
特に私は、三鷹市長在任中に【コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育】を創始し、保護者・地域住民・有識者参加の【学校運営協議会】のご活躍の意義を痛感している経験から、学校における働き方改革の実施の確保には、学校運営協議会で検討していただき承認を得る事は極めて有意義と考えるのです。
会議の席の左のお隣は、私の母校である慶應義塾大学の伊藤塾長で、右のお隣は埼玉県戸田市の戸ヶ崎勤教育長でした。
会議の前後で、お2人をはじめとする委員の皆様や事務局の文部科学省の皆様との会話の時間をいただけることが、とても幸いなことです。
会議室を出てからも、森朋子・桐蔭横浜大学学長とお話しさせていただきました。
森学長は、学習理論・学習研究者であり、現在は大学の学長をされていますが、小学校長も経験されており、初等中等教育のご経験をお持ちです。
委員の皆様の会議でのご発言から学ぶことはもちろん多いのですが、会議前後の短い会話で得ることができる、委員の皆様との人間性のにじみ出る出逢いと対話が、私に大いなる力を与えてくれます。
審議会の委員を務めさせていただいていることの有難さに感謝の気持ちでいっぱいです。


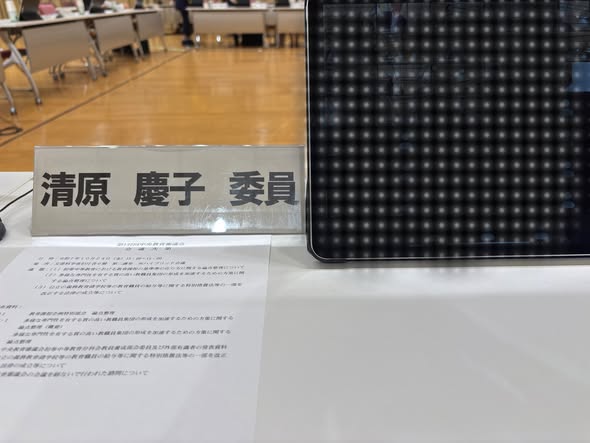
 清原慶子 Official Website
清原慶子 Official Website




